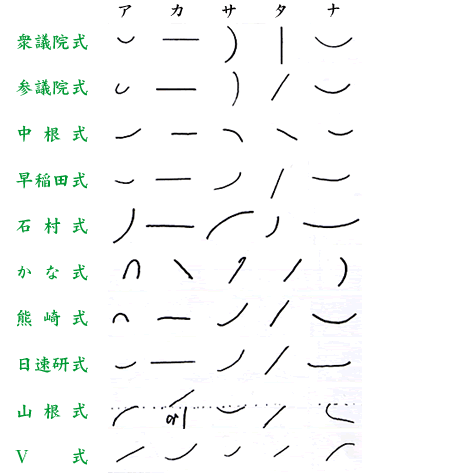言葉の記録の世界でも 人間技が今後も大いに活躍します。
速記の知識
実はあなたも使っている 速書き文字!
だれでも使っている略字といえば 郵便番号 → 〒 ではないでしょうか。
また、英語の頭文字もよく使われています。日本放送協会 → NHK、日本航空 → JAL このように、いろいろな方法を使って、何とか速く表現しようとすることが多いです。
では、漢字を書く場合はどうでしょうか。漢字は ”自分流の行書” で書く ことが多いと思います。さらに、漢字を書く時間がないときは、仮名文字を書きますが、これはまさに ”千年前からの速記文字” と言えます。
つまり、漢字をくずしていってひらがながつくられました。漢字の一部を取ってカタカナがつくられました。どちらも漢字を書くよりもはるかに速く言葉を表現できますから、非常に便利に活用されてきました。
しかし残念なことに、仮名文字は”速記文字”とは認識されませんでした。
ところで、ひらがなの中で最も簡単なものは「し」と「く」と「つ」です。カタカナの中では「ノ」が最も簡単です。つまり、1本の線で表現できるからです。45文字が全部一本の線で書けるようになっていれば、それだけでも非常に簡単に書けることになります。そして、それに最も近づけるように研究されてきたのが、いわゆる「速記文字」なのです。
本格的な速記が生まれてから120年
日本には2種類の仮名文字があり、これらを使って少しは速く書けたために、本格的な速記法の研究は行われませんでした。しかし、明治時代になってから、人の話を書き取ることができる本格的な速記の研究が始まりました。そして、田鎖綱紀の研究によって、明治15年に田鎖式が発表!されました。これが日本の本格的な速記の始まりです。
田鎖式は衆議院と参議院 (当初は貴族院) に採用され、やがて衆議院式、参議院式に分かれました。
その後、研究が続けられ、熊崎式(明治39年)、中根式(大正3年)、早稲田式(昭和5年)などの方式が発表されました。現在でも検定試験の受験者を出している速記方式としては、上記の4方式の他、石村式、かな式、熊崎式、日速研式、山根式、V式などがあります。これらの速記文字が書ける人の中から速記者が出て、非常に重要な仕事をしてきました。今日でもその能力が高く評価されています。
各方式の 「アカサタナ」